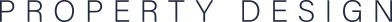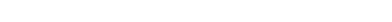告知事項あり物件とは? 完全ガイド
初めて「告知事項あり」を見かけた方向けに、意味・メリット/デメリット・選び方のコツまで、実務視点でまとめました。
この記事のポイント
- 「告知事項あり」= 契約の判断に影響しうる重要情報(瑕疵)がある物件
- 瑕疵の種類は主に心理的・環境的・物理的・法的の4つ
- ガイドライン上、自然死などは原則告知不要だが、特殊清掃が伴う場合や自殺・他殺・火災等は告知対象に
- 賃貸では概ね3年を目安に告知不要とされる場合もあるが、社会的影響が大きい事案や問合せがあった場合は告知が必要
- メリット(相場より割安・条件緩和等)と、デメリット(精神的負担・住所特定リスク等)を総合判断する
※本記事は一般的な解説です。個別事情や地域の運用で異なる場合があるため、最終判断は宅建業者・専門家へご確認ください。
「告知事項あり物件」とは
告知事項あり物件とは、借主(入居者)の契約判断に重要な影響を及ぼし得る瑕疵(かし)が認められ、貸主側が事前に告知する義務が生じている物件のことです。ここでいう瑕疵とは「傷・欠点」に限らず、心理的抵抗や生活の支障につながる要素も含みます。
4つの瑕疵
- 心理的瑕疵:自殺・他殺・火災による死亡、長期間の孤独死など、入居者に強い心理的抵抗を与える事柄
- 環境的瑕疵:周辺の騒音・臭気・振動、治安や周辺施設(工場、ギャンブル施設、風俗店、墓地・火葬場、宗教施設、高圧線鉄塔、ゴミ・下水処理場 等)による生活上の不利益
- 物理的瑕疵:建物や土地自体の欠陥(シロアリ被害、雨漏り、ひび割れ、傾き、耐震性不足、アスベスト使用など)
- 法的瑕疵:法令・条例等により利用や再建築が制限される、あるいは違反状態である(建ぺい率・容積率超過、再建築不可、消防設備不備 など)
なぜ「告知」が必要?(基本ルール)
不動産取引では、売主・貸主は重要な事実を正確に伝える義務があります。特に人の死に関する心理的瑕疵はトラブルになりやすいため、国のガイドラインで調査・告知の考え方が示されています。
告知の考え方(要点)
- 自然死や日常生活上の不慮の事故(転倒・入浴中の事故・誤嚥等)は、原則として告知不要。
- ただし、特殊清掃(遺体の損傷等により衛生上の措置が必要な清掃)が行われた場合は、原則告知。
- 自殺・他殺・放火・火災等は、原則告知。
- 賃貸では、上記の事案が発生してから概ね3年経過した後は、原則告知不要と扱われる場合がある。
- ただし、事件性・社会的影響・周知性が特に高い場合や、借主から質問があった場合は、経過年数にかかわらず告知が必要。
- 共用部(エントランス・廊下等)での事案も、入居者が日常的に使用する場合は告知対象になり得る。
ここに挙げたのは要点です。実務では、個別の事案と地域の運用、裁判例の蓄積等を踏まえて総合判断します。
メリット・デメリット
メリット
- 賃料が相場より抑えられる傾向:心理的ハードルや募集の難易度から、相場より低めに設定されるケースがある。
- 募集条件が柔軟:礼金ゼロ・フリーレント・設備追加・家具家電付きなど、条件交渉が通りやすいことも。
- リフォーム/リノベ済みの可能性:印象改善のため内装や設備を刷新している場合がある。
デメリット
- 精神的負担:入居後に気持ちの負担が増えることがある(在宅勤務で騒音が気になる等、環境要因も含む)。
- 住所特定・訪問リスク:有名事案だと、物件が特定される場合があり、見物や勧誘・営業等の煩わしさにつながることも。
告知事項の具体例
- 心理的:対象住戸での自殺・他殺・火災による死亡/長期間発見されなかった孤独死 等
- 環境的:線路や幹線道路に面し騒音が常時発生/工場や下水処理施設由来の臭気/繁華街近接による治安不安 等
- 物理的:著しい雨漏り/構造クラック/配管破損による水圧低下/耐震基準不適合/シロアリ被害 等
- 法的:再建築不可/建ぺい率・容積率超過/消防設備不備/市街化調整区域での制限 等
注:経年劣化(床の小傷、パッキンの摩耗 等)は通常の瑕疵に当たりません。
選ぶ際のポイント
- 心理的瑕疵が告知されない場合がある:特定の条件を満たせば、一定期間経過後は告知不要と扱われることがあるため、気になる点は必ず質問を。
- 許容範囲の見極め:内見は昼・夜/平日・休日の複数回を推奨。音・光・におい・人通り・治安を確認。
- 新築でもゼロではない:工事中の事故、完成後の周辺環境変化、施工不備等により瑕疵が発生する可能性はある。
よくある質問(FAQ)
Q1. どこまで説明してもらえますか?
A. 借主の判断に重要な影響を与える事項は説明義務があります。気になる点は遠慮なく具体的に質問しましょう(例:発生年月、場所、内容、再発防止策 等)。
Q2. 相場より家賃が安いのはなぜ?どのくらい安くなりますか?
A. 募集の難易度や心理的ハードルを踏まえ割安となる傾向がありますが、事案・地域・市場環境で幅があります(一律の目安はありません)。
Q3. 入居後に知らされていない事実が判明したら?
A. まずは仲介会社・貸主へ事実確認を依頼。対応が得られない場合は、自治体の消費生活センターや宅建協会等の相談窓口へ相談しましょう。契約内容や立証状況により、契約解除・損害賠償が問題となることがあります。
Q4. 共用部での事案は対象になりますか?
A. 日常的に使用する共用部(廊下・階段・エントランス等)での事案は、告知対象とされる場合があります。
Q5. こちらから質問した内容は、経過年数に関係なく答えてもらえますか?
A. はい。 借主からの質問があれば、経過年数や死因に関わらず告知が必要とされています。
トラブル事例と対応の流れ
事例:「告知事項あり」と表示されていたが、契約時に詳細説明がなかった
対応:
- まずは仲介会社に説明要求(書面の提示含む)
- 貸主へ事実確認を依頼
- 解決しない場合は、自治体の相談窓口/消費生活センター/宅建協会へ相談
相談窓口は自治体ごとに名称や受付時間が異なります。お住まいの地域の公式サイトでご確認ください。
まとめ
- 「告知事項あり」は、心理・環境・物理・法的のいずれかの重要事項が存在するサイン。
- 自然死は原則告知不要だが、特殊清掃を伴う場合や自殺・他殺・火災等は原則告知。賃貸では概ね3年を目安に告知不要となる扱いがある一方、社会的影響が大きい事案や質問があった場合は告知が必要。
- メリット(割安・条件柔軟・リフォーム済み等)とデメリット(精神的負担・特定リスク)を総合的に比較し、複数回の内見と書面確認で判断しましょう。