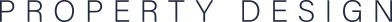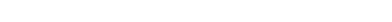築古物件と築浅物件の違いとは?築年数の目安や特徴、耐用年数まで詳しく解説
賃貸物件を探すとき、「築古(ちくふる)」や「築浅(ちくあさ)」という言葉をよく耳にしますよね。
これらは物件の築年数を表す言葉で、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。賃貸物件選びの際に知っておくと役立つ情報です。
また、物件選びでは「耐用年数」もチェックポイントのひとつ。法的に定められた建物の使用可能期間の目安で、物件の状態や将来のメンテナンスに関わる重要な指標です。
この記事では、築古物件と築浅物件の具体的な築年数や特徴、メリット・デメリットに加え、法定耐用年数についても詳しくご紹介します。これから賃貸物件を探す方はぜひ参考にしてください。
築古物件とは?築年数の目安と主な特徴
「築古物件」とは、名前の通り築年数が長い物件のことを指しますが、具体的にはどのくらいの築年数なのでしょうか?
一般的に、築古物件は築30年以上の物件を指すことが多いです。ただし、不動産業界での明確な定義はなく、会社によっては25年以上を築古と呼ぶこともあります。逆に、築年数が30年以上でも状態が良ければ築古とは言わない場合もあるため、あくまで目安と考えてください。
築古物件のメリット
-
家賃が比較的安い:築年数が経つほど物件の価値は下がるため、家賃もリーズナブルになる傾向があります。
-
リフォーム・リノベーション済み物件が多い:築古でも内装や設備が新しく改装されていることがあり、新築に近い快適さを低価格で得られることがあります。
築古物件のデメリット
-
設備の老朽化リスク:長年使われているため、設備の劣化や不具合が発生している場合があります。
-
内覧時の注意点が多い:水回りの状態や床のきしみなど、劣化が顕著に表れやすい箇所をしっかりチェックしましょう。
築浅物件とは?築年数の目安と主な特徴
「築浅物件」は築年数が浅い新しい物件を指しますが、こちらもはっきりした基準はありません。
多くの場合、築5年以内の物件を築浅と呼びますが、不動産会社によっては7年以内を築浅とすることもあります。
また「新築物件」と築浅物件は厳密に区別されています。
新築とは「建築工事完了後1年以内で、まだ一度も人が住んでいない物件」を指し、築浅物件には新築を含みません。
築浅物件のメリット
-
設備や内装が新しく快適:最新の設備が備わっており、生活の満足度が高いことが多いです。
-
セキュリティ面が充実:オートロックなど最新の防犯設備が備わっている物件も多く、特に女性や学生の方に安心感があります。
-
建物の状態が良好:室内外の劣化がほとんどないため、トラブルが少ない傾向にあります。
築浅物件のデメリット
-
家賃が高め:設備や環境の良さから人気があり、家賃が高くなることが多いです。
-
化学物質の影響:新築同様、建材や接着剤などから化学物質が発生し、アレルギー反応を起こす可能性があります。ただし、24時間換気システムの義務化により、このリスクは減少傾向にあります。
建築構造別の法定耐用年数について
物件選びの際にぜひ知っておきたいのが「法定耐用年数」です。
これは、建物が法的に認められた使用可能期間の目安で、税務処理のために定められています。
法定耐用年数は建物の寿命とは異なり、実際の使用可能期間がこれより長いケースも多いですが、修繕やリフォームのタイミングの参考になります。
主な建築構造の法定耐用年数は以下の通りです。
-
木造:22年
-
鉄骨造(骨格3mm以下):19年
-
鉄骨造(骨格3mm超4mm以下):27年
-
鉄骨造(骨格4mm以上):34年
-
鉄筋コンクリート造(RC造):47年
築古物件はこの耐用年数に近づくと大規模な修繕が行われている場合が多く、物件の状態を把握するポイントになります。
まとめ
-
築古物件は一般的に築30年以上。家賃が安い反面、設備の劣化リスクがあります。
-
築浅物件は築5年以内。設備やセキュリティが新しく快適ですが、家賃は高めです。
-
法定耐用年数は建物の使用可能期間の目安で、構造によって異なります。
物件選びでは、築年数の目安だけでなく、実際の状態や設備の状況を確認することが大切です。内覧時には気になる点を細かくチェックし、自分のライフスタイルや予算に合った物件を見つけてください。